22歳、夢だった教師の世界へ
22歳で飛び込んだ世界は、私の将来の夢でもあった小学校の先生だった。
子どものころからの憧れを現実にするため、大学4年間はずっとその夢のために準備してきた。
「出会う子どもたちを、少しでも幸せにしたい」——そんな志を胸に、私は新しい春を迎えた。
現場では「元気だね」「笑顔がいいね」と言ってもらえることも多かった。
でも、教師として一番大事な授業力は、ぜんぜん足りていないと痛感していた。
指導を受けながら必死に学び、少しでも良い授業をしようと努力していたけれど、
その世界は想像していた以上に厳しく、立ちはだかる壁は次々に現れた。
校内研究、校務分掌、教科ごとの準備、保護者への対応、朝の活動、放課後の行事…。
教育実習ではほんの一部しか体験できなかった現実の業務が、洪水のように一気に押し寄せてきた。
私はもともと、何事にも人より少し時間をかけないと呑み込めない性格。
その性格もあって、朝4時58分の始発で出勤し、夜は11時20分の終電で帰るような毎日が続いた。
周りの先生に頼ることも下手で、「笑顔の鎧」をまとって本音を隠し、心の中はどんどん窮屈になっていった。
倒れた日
なんとか1学期を終え、終業式を迎えた。
夏休みも積極的に日直を代わり、授業準備に没頭した。
疲れはどれだけ休んでも取れなかったけれど、「助けて」は言えなかった。
言ってしまったら終わりかもしれない——そう思っていたから。
2学期の始業式。
みんなが「暑いね」と笑いながら半袖で並んでいたその日、私は寒くてカーディガンを脱げなかった。
それでも、体育館で子どもたちの姿を見て「また頑張ろう」と思っていた——その瞬間、意識が途切れた。
気がつくと倒れていて、身体が動かなかった。
息が荒く、世界がチカチカ光っていた。涙も出なかった。
次の日から、私の世界はまた止まった。
玄関に立つと、動悸と吐き気で外に出られない。
病院では過労と鬱の悪化を告げられ、3か月の休職をすすめられた。
壊れていく部屋、壊れていく心
今回は、大学のときとは違った。
自分だけでなく、職場や子どもたちに迷惑をかけたという罪悪感でいっぱいだった。
何度も自分を責めても、どうにもならなかった。
1か月、2か月——私はベッドの上でただ寝て起きるだけの生活を続けていた。
部屋はゴミがあふれ、洗い物も溜まり、「健康的な生活」がどんどん遠ざかっていった。
限界を感じ、母に助けを求めた。
でも、母は「離婚後は自分のことで精一杯だから、面倒は見られない」と言った。
悲しかったけれど、どこかで「仕方ない」とも思った。
私はもう、誰にとっても荷物なんだと思い込んで、心を閉ざした。
父が迎えに来てくれた日
そんなある日、突然、父が私の一人暮らしの部屋にやってきた。
「死んでしまう前に、山梨に帰ろう。もうやめて、帰ろう。」
その言葉に、張りつめていた糸がぷつんと切れた。
離婚以来、父とはどこか気まずくなっていた。
でも、その父が——母から「いらない」と言われた私を迎えに来てくれた。
それがどれほど救いだったか、言葉にならない。
あの日、父が来てくれたことが、希望だった。
その日のうちに実家へ戻り、1週間ほど眠り続けた。
祖母と父と弟が、交代で私の面倒を見てくれた。
やがて、少しずつ食事ができるようになり、私は退職を決意した。
立ち止まって、もう一度
「まずは、体と心を整えよう。仕事より、いまは生きることを取り戻そう。」
そう思えるまでに時間はかかった。
校長先生や副校長先生に退職を伝えるとき、緊張で震えが止まらなかったけれど、
自分の言葉で伝えられたことが、心のわだかまりを解く一歩になった。
それからの1年は、「回復すること」だけに向き合った。
病院に通い、人と少しずつ話し、食事をして眠るという「ふつうの生活」を取り戻していった。
そしてようやく気づいた。
頑張ることも、休むことも、生きるために必要な力なのだと。
生きることは、全力だけじゃなくてもいい。
ゆっくりでも、また一歩ずつ歩ければいい。
過去を受け入れて、今を生きる
22歳で倒れたあの日、私は「生きること」をもう一度考えた。
夢を叶えた先で壊れてしまった自分を、少しずつ拾い集めていく。
そして今、あの過去もすべて、自分を形づくる大切な一部なんだと受け入れられるようになった。
悲しみも、痛みも、私の中にちゃんとある。
でも、それを抱えたままでも、私は今日を生きている。
過去を受け入れて、今を生きる。
それが、私の「ゆるやかに生きる」1mmだった。


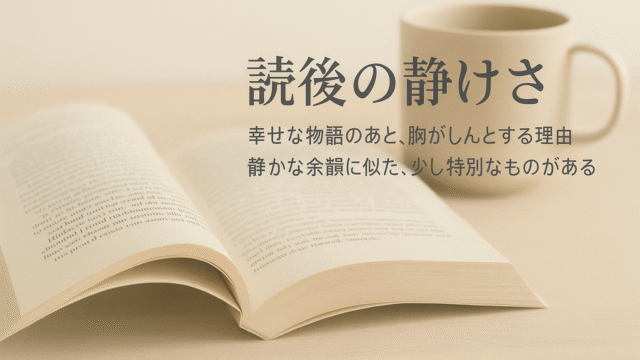
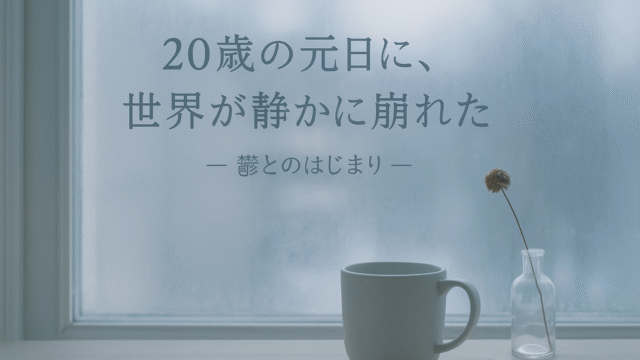




 タイトルを入力してください
タイトルを入力してください 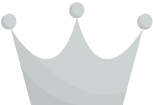 タイトルを入力してください
タイトルを入力してください 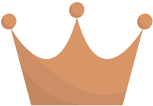 タイトルを入力してください
タイトルを入力してください